
カテゴリー別アーカイブ: 日記
”よく噛んで食べてほしい。”
新年あけましておめでとうございます。
旧年中は、保護者の皆様や地域の皆様方に、大変お世話になりました。ありがとうございました。
本年もよりより園、よりよい保育を目指して邁進してまいりますので、変わらぬご支援のほど、よろしくお願いいたします。
昨年末に、保育に関する記事を投稿し損ねてしまったので、今月は2本投稿いたします。今年もコツコツ地道に執筆しますので、ご興味のある方はぜひご覧ください(^^♪
園長








「充実した食環境を」
私たちがほぼ毎日必ず行うことのひとつに、「食事」があります。
食事に関して、「よく噛んで食べることが大切」ということは、多くの方が耳にしたことがあるのではないでしょうか。
噛むこと(咀嚼)は、単に食べ物を飲み込むための行為ではありません。
こどもの身体的・認知的・情緒的な発達に深く関わる、とても重要な行為なのです。
例えば、噛むことで脳の血流が増え、特に前頭前野が活性化する可能性が示唆されています。
前頭前野は、注意・集中、感情のコントロールなどを司る部位で、学習や対人関係、日常生活のあらゆる場面に関係しています。
また、一定のリズムで噛むことは副交感神経を優位にし、心身を落ち着かせる効果があるとも言われています。
ガムを噛むことで緊張や不安が和らぐ可能性が示されており、スポーツ選手が集中力を高めるためにガムを噛んでいる姿を目にすることもありますね。
さらに、顎の骨や口周りの筋肉が発達することで、
・歯並びが悪くなりにくい
・発音が明瞭になりやすい
・姿勢が整いやすい
といった効果もあるとされ、古くから「咀嚼の大切さ」は言い伝えられてきました。
(エビデンスレベルはまちまちですが、「卑弥呼の歯がいーぜ」という語呂合わせで咀嚼の効果が説明されることもあります。)
しかしながら、現代は「よく噛んで食べる」習慣が育ちにくい環境でもあります。
加工食品やファストフード、柔らかい食事が増え、短時間で食事を済ませたり、「ながら食べ」をする機会も多くなりました。
国が実施している「乳幼児栄養調査」を見てみると、
昭和60年:1~4歳未満で「よく噛まない」子が10.2%
平成7年:12.6%
平成17年:20.3%
と、「よく噛まない」子の割合が年々増加していることがわかります。
平成27年以降は調査方法や集計方法が変わっているため単純な比較はできませんが、
離乳食期の0~2歳児で丸のみをしている子が約3割、
2~3歳未満でも「よく噛まない」子が16%程度いると報告されています。
すなわち、現代においてもおおよそ3~5人に1人は、食べ物を十分に噛まずに飲み込んでしまう傾向があると考えられます。
(現在、令和7年調査が行われており、結果は来年9月頃に公表予定です。最新情報については、改めてお知らせしたいと思います。)
では、「よく噛んで食べる」習慣は、どのように身につくのでしょうか。
私は、乳幼児期からの充実した食体験の積み重ねが、ひとつの大きな鍵になると考えています。
一般に咀嚼の仕方や食べ方は、繰り返しの経験によって習慣として定着していく行動だと考えられています。
特に乳幼児期は、神経系や運動機能が発達の途中にあり、日常的な行動が身につきやすい時期です。
最近、乳幼児の食事で少し気になっているのが、のどに詰まらせることを心配するあまり、過剰に細かく・柔らかくしすぎているケースです。
細かくしすぎると噛む必要がなくなり、丸のみの習慣がつきやすくなります。
また、食材の形がわからないことで、「何を食べているのか」がこども自身に伝わりにくくなるという側面もあります。
「何を食べているかわからない」という状態が毎食のように繰り返されることも、「よく噛まない」食べ方につながる可能性があります。
なぜなら、研究や調査において、「食への興味・関心が高い」ことと「よく噛む」ことには関連があることも示されているからです。
刻み過ぎて食材が分かりにくい状態は、単に丸のみを助長するだけでなく、食への関心が育ちにくいという方向性からも、咀嚼する習慣の形成を阻害する要因になってしまう可能性もあるのです。
咀嚼習慣は、離乳食開始から、数年かけて形成されます。
離乳食期や、まだ幼い年代のお子さまに取り組んでほしいことは、手づかみ食べ・かじりとりです。
1.前歯で一口量をかじり取る
2.奥歯で噛み砕く
3.舌でまとめて飲み込む
こうした一連の動きを離乳食期から繰り返すことで、適切な一口量や噛み方、口周りの筋肉の使い方を、こどもは自然と身につけていきます。また、手づかみ食べでは、スプーン等を介さず、直に手で触れることにより、食材の温度、かたさ、触感などを指や掌から感じ取っていきます。これらの経験により、食材や料理のイメージが豊かに形作られていくことになります。
「噛む力を育てる献立や取り組みを考えるのは難しい」
「外食に頼らざるを得ない」
そんなご家庭も多いと思います。でしたら、こんなアプローチもあります。
実は、
・朝食を誰かと一緒に食べる
・家族で会話をする時間がある
こうした環境にあるこどもほど、「よく噛んで食べる」傾向があることもわかっています。
誰かと一緒に食べたり、落ち着いた雰囲気の中で食事をしたりする経験は、食への肯定的な気持ちを育てる大切な要素です。
園では、日々の給食や野菜栽培、調理体験、食に関する行事などを通して、こどもたちの食に対する前向きな気持ちを育んでいきます。
ご家庭でも、忙しい日々の中ではありますが、よりよい咀嚼習慣を身につけるためのアプローチをしてみませんか。食事内容を見直したり、同じ食卓で同じ時間に食事をとるようにしたり、家族団らんの時間をできる限り確保したりするなど、方法はなんでも構いません。毎日、毎食でなくても大丈夫です。少しずつ積み重ねていきましょう。それが、お子さまの将来の健康につながります。
食の悩みは、ひとりで抱え込まなくて大丈夫です
先述の「乳幼児栄養調査」では、約8割の保護者がこどもの食事について悩みを抱えていることもわかっています。
5人に4人が、同じように悩んでいるということです。悩みがあるのは当たり前です。
食事のことで気になることがあれば、どうぞお気軽に、私たち保育者や栄養士等にご相談くださいね。
※ちなみに、今回は「かまない」子の話題ですが、「乳幼児栄養調査」では、平成17年に「口から出す」という質問項目が追加され、27年には「食べ物を口にためる」という項目が追加されていることから、「かめない」「飲み込めない」子の存在も徐々に認識されてきているものと考えられます。この話は、またいつか。
本日の園の様子
今週と来週は、連絡帳の代わりに園の様子の一部をお届けします(^^♪
空手にお散歩に、お外遊びに…と、各々の活動を楽しんでいたこども達でした。2月のマラソン大会も近づいてきているので、鬼ごっこなどの走りを伴う遊びも活発に行われるようになってきました。お父さん、お母さんも走るかもしれませんので、おこさまに置いていかれないよう、体力をつけておいてくださいね。笑
明日はいよいよ、未満児さんのおゆうぎ会です。楽しんでステージに立ってくれることを願っています!登園管理はいつも通りアプリで行いますので、タグをお忘れにならないように。
明日もよろしくお願いいたします!
園長
















※活動の場所やタイミングの関係で、撮れていないクラスがあります。来週は撮れるようにしますね。すみません。
”文脈を楽しみましょう”
すっかりと寒くなったかと思いきや、今日の昼は半袖でもいいぐらいポカポカで。今日は未満児さんのお散歩に同行しました。前に通った時よりも、果実が熟していたり、植物が枯れていたり、季節の変化を楽しみながら足取り軽やかなみんなでした。
11月も最後の開園日を迎え、今年も残すところあと1ヶ月となりました。
残り1ヶ月、感染症に気を付けながら外でいっぱい遊びたいところですね。
今月も、写真のあとに保育・子育てに関してちょっと語りますので、ご興味ある方はぜひご覧ください(^^♪
今月もありがとうございました。来月もよろしくお願いいたします!
園長




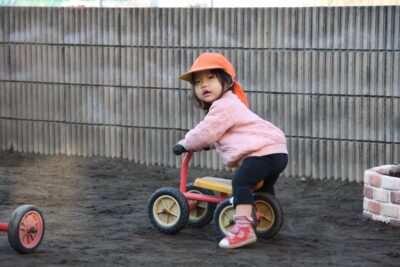



先日園庭で遊んでいると、ある場面を目撃しました
AくんとBくんがボールの取り合いになっていました。取り合いはやがて叩きあいに発展し、AくんはBくんに顔をたたかれ、泣き出してしまいました。
そこにCくんがかけつけてきて、「Bくんなにしてんの!、Aくん、一緒に遊ぼう」と手を引いていきながら、Bくんには「はいってこないでよ!」と告げていました。
みなさんは、このCくんの行動をどう思われますか?善いですか?悪いですか?それはなぜですか?どんな声掛けが必要だと思いますか。
これだけの情報だと、わかりませんよね。背景がわからないからです。
単純に、Aくんへの思いやりからの行動かもしれませんし、ボールを手に入れるという目的達成のためのアライアンスかもしれません。また、“仲間外れ”の行動の背景には、「悪人に対する悪は許される」というような考えが存在する可能性も考えられます。
それぞれ、どのような考えで、どのような問題があり、どのような対応が考えられるかと話していくと長すぎるのでやめておき、私が今回述べたいのは、場面を切り取ってはいけないということです。
ちょくちょく「私は全部見ていた」という人がいますが、一部始終を見ていたとしても、それが“全体”ではありません。
人は人生という文脈の中で生きていますから、午前中や昨日、先月等々、過去と繋がった今を生きています。どんな行動にも、背景や考えがあります。文脈によって、とっている行動の意味の解釈は大きく変わります。意味が変わると同時に、同じ行動の社会的価値が善から悪に、悪から善に一転することもあるわけです。
見せかけだけをとらえて背景がわからないままでは、明後日の方向の声掛けをしてしまうかもしれません。ですから、われわれおとなには、こどもの表出する行動や言動だけにとらわれない考え方が求められます。こどもを観察したり、対話したりしながら、文脈を丁寧に紐解いていく必要があります。
年齢が上がるほど、喋られるようになるからわかりやすくなるかと思いきや、直接的ではない争いの様相が現れ始めますし、攻撃の様相を呈さない攻撃も行われるようになります。
大人から見た“よい子”な振る舞いが、ただの攻撃衝動、快楽衝動だということもありますし、”困った子“な振る舞いが、他者への思いやりだったりもするわけです。
見せかけにとらわれず、こどもの人生の文脈を楽しんでみてください。小さくてもちゃんといろいろ考えていますから、とってもおもしろいですよ。
”がんばる?”
10月11日に、運動会が行われました。
今年度は、保護者参加型の種目が多く、家族みんなの笑顔あふれる運動会になったのではないかと思われます。
運動会のねらいは、「うんどうするってたのしいな」と感じてもらうことです。それは、運動会の本番だけが楽しければ良いのではありません。
運動会への動機づけから始まり、練習期間、本番、そして終わってからの日常という一連のプロセスの中で、からだを動かす楽しさ、心地よさを味わってほしいなと思っています。
そのきっかけとして、運動会が設定されているだけであり、運動会本番が全てではありません。「運動会は楽しかったけど、練習はもうやりたくない」、「運動会が終わったから、もう運動したくない」みたいになってしまっては意味がありません。
そういった視点からこども達を観察すると、今も活発に体を動かして遊んでおり、ねらいに迫るいい運動会になったのではないかと思われます。ご協力いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。
今月も写真のあとに保育についてちょっと語りますので、お時間のある方はぜひご覧ください。














今月は、せっかくなので運動会をテーマに書きたいのですが、運動会だけで10個ぐらい記事が書けそうでテーマ設定に悩みます…。行事になると、「がんばる」が重視されがちなところがありますので、いつか書こうと思っていた、「がんばる」について考えてみたいと思います。そもそも、がんばるって何?という話は、長くなるので置いておいて…。挑戦的なタイトルなので、モヤっとしながら読み始めていただいて、最終的にモヤモヤが解消されれば幸いです。
「こどもはがんばりません」
人は、自分のやりたいことに夢中になって取り組んでいるとき、本質的には頑張っているのかもしれませんが、当事者の意識としては、まったく頑張っていません。そういった意味で、こどもに「頑張らせない」ということが、重要な視点のひとつだと考えています。私もよく「頑張ってるね」と言われますが、やりたいことをやっているだけなので、まったく頑張っていません。
保育園で大事にしたいのは、こども一人ひとりの内側から湧き出てくる興味・関心を、とことん突き詰めていくことです。自分がやりたいことに夢中になって取り組む状態になりやすいので、端から見ていると「がんばっている」ように見えます。
一方で、大人にほめてもらいたくてとか、怒られるのが嫌だからとか、外からの力で“頑張らされて”いる状態もよく見かけます。これも同様に、端から見ると「がんばっている」ように見えます。
どちらも「がんばっている」ように見えてしまうので、同じものだと認識されてしまいがちです。
ここの区別がつかずに、実際はがんばらされているのに、やりたいことだと誤解されて、さらに頑張らされてしまうのは恐ろしいです。一方で、やりたいことに夢中になっているのに、「そろそろ休んだら?」、「違う遊びもしたら?」みたいに水を差されてしまって台無しになるのも恐ろしいです。
ここを区別し、見極める力が、保育者や保護者など、こどもと関わる人には大事だと思っています。
ずーっと“がんばらされてきた”こどもは、次第に内側から湧き出てくるものがなくなり、自分で目標を見つけて努力をする力を失います。がんばらせてくれる人が近くにいないと、何もできない人になります。「やりたくないことも頑張ることで成長する」とか、大人は都合のいいように色々言いますが、がんばらせなくても成長します。自分の興味のあることを、自分で工夫しながら、その周りにあるものも含めて、大人も驚くほどのレベルまで。
私は、夢中になってキラキラしているこどもの目が大好きです。笑顔でも、真剣な顔でも、集中して口があいてしまっている顔でも、その目の奥から感じる生き生きとしたものがあります。がんばらされて光のない目とは、全然違います。
行事や保育の内容も作り替えていきながら、よりよい園にしていきたいですね。
誤解が生じないように最後に念のため、
「大人のやらせたいことを、頑張らせる保育」は、その場の見せかけはいいかもしれませんが、こどもの主体性をはじめとする様々な資質を奪います。
当園では、「こどもが自分の興味のあること、やりたいことに夢中になる保育」を目指します。
今月もありがとうございました!来月もよろしくお願いいたします!
園長

















